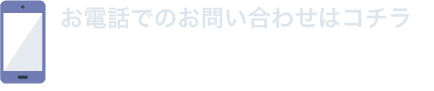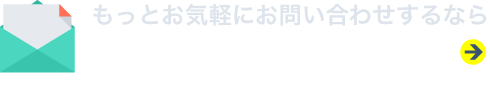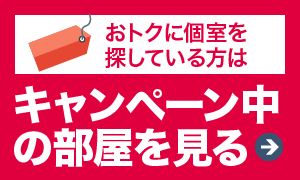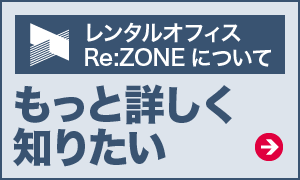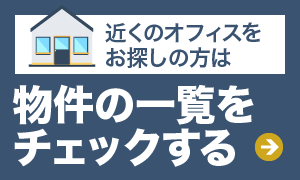リモートワークや在宅勤務など働き方の多様化が浸透する中、「ワークシェアリング」が注目を集めています。ライフワークバランスの実現だけでなく、長時間労働や過労といった社会問題の解決策としても有用な考え方で、国内ではワークシェアリングを導入する企業も増えています。今回は、ワークシェアリングについて、定義や事例を用いて詳しく解説します。日本でも重要視されるようになった背景や、より効果的に導入するための課題についてもまとめています。ワークシェアリングの導入を検討している企業や担当者の方、ワークシェアリングという働き方に興味がある方はぜひご覧ください。
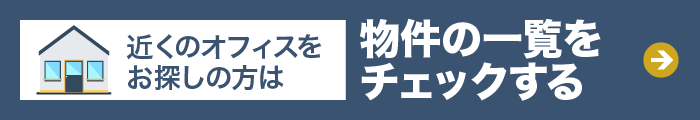
ワークシェアリングとは?
 ワークシェアリングとは、一言で言うと「1個人の労働量を複数人で分け合うこと」です。厚生労働省では、「雇用機会、労働時間、賃金」という3つの要素の組み合わせを柔軟に変化させ、業務の分担を効果的に行うとしています。ワークシェアリングは、1人当たりの負担軽減や長時間労働の改善、社会全体における雇用機会の増加を目的としています。ワークシェアリングによって、労働条件の改善とともに、企業の生産性向上や効率性アップといった効果も見込めます。日本においては政府の働き方革命の推進施策として注目されており、海外の事例を受けて国内でも導入企業が増加傾向にあります。
ワークシェアリングとは、一言で言うと「1個人の労働量を複数人で分け合うこと」です。厚生労働省では、「雇用機会、労働時間、賃金」という3つの要素の組み合わせを柔軟に変化させ、業務の分担を効果的に行うとしています。ワークシェアリングは、1人当たりの負担軽減や長時間労働の改善、社会全体における雇用機会の増加を目的としています。ワークシェアリングによって、労働条件の改善とともに、企業の生産性向上や効率性アップといった効果も見込めます。日本においては政府の働き方革命の推進施策として注目されており、海外の事例を受けて国内でも導入企業が増加傾向にあります。ワークシェアリング厚生労働省による4つの類型
日本におけるワークシェアリングについて、厚生労働省は目的ごとに下記4つの類型に分類しています。《引用》(1) 雇用維持型(緊急避難型):一時的な景況の悪化を乗り越えるため、緊急避難措置として、従業員1人あたりの所定内労働時間を短縮し、社内でより多くの雇用を維持する。(2) 雇用維持型(中高年対策型):中高年層の雇用を確保するために、中高年層の従業員を対象に、当該従業員1人あたりの所定内労働時間を短縮し、社内でより多くの雇用を維持する。(3) 雇用創出型:失業者に新たな就業機会を提供することを目的として、国または企業単位で労働時間を短縮し、より多くの労働者に雇用機会を与える。(4) 多様就業対応型:正社員について、短時間勤務を導入するなど勤務の仕方を多様化し、女性や高齢者をはじめとして、より多くの労働者に雇用機会を与える。引用元:厚生労働省多様就業対応型には、正社員とパートタイム、兼業・副業、在宅勤務といった施策も含まれます。また、未経験者や若い世代への教育訓練等を通じて、一人前の職業人に育てるためのプログラムやOJT研修も有効です。ワークシェアリングが誕生した意味と背景
 ワークシェアリングの基本的な考え方としては、仕事量が多い人が他の人の助けを借りるために、仕事のない人を雇用する手法です。失業率の高さが問題であった時代に、ヨーロッパ型社会民主主義に基づき採用されました。日本でワークシェアリングが提唱され始めたのは2000年頃ですが、後に長時間労働や過労が社会問題として深刻化するにつれ、ワークシェアリングの必要性が強く呼びかけられるようになりました。アルバイトやパートと正規雇用との賃金格差の大きさや、役割や責任の不明瞭さなどが原因となって導入が先送りにされてきましたが、「健康経営」の重要性が訴えられている近年、ワークシェアリング導入を前向きに検討する動きが増えています。
ワークシェアリングの基本的な考え方としては、仕事量が多い人が他の人の助けを借りるために、仕事のない人を雇用する手法です。失業率の高さが問題であった時代に、ヨーロッパ型社会民主主義に基づき採用されました。日本でワークシェアリングが提唱され始めたのは2000年頃ですが、後に長時間労働や過労が社会問題として深刻化するにつれ、ワークシェアリングの必要性が強く呼びかけられるようになりました。アルバイトやパートと正規雇用との賃金格差の大きさや、役割や責任の不明瞭さなどが原因となって導入が先送りにされてきましたが、「健康経営」の重要性が訴えられている近年、ワークシェアリング導入を前向きに検討する動きが増えています。ワークシェアリングの事例【国内・海外】
 実際にワークシェアリングを導入している国や企業の事例を見ていきましょう。日本よりも先にワークシェアリングを採用し、効果を出しているオランダや、国内で取り入れている大手企業のケースを紹介します。自社への取り入れ方や個人の働き方をより具体的にイメージするために、ぜひ参考にしてください。
実際にワークシェアリングを導入している国や企業の事例を見ていきましょう。日本よりも先にワークシェアリングを採用し、効果を出しているオランダや、国内で取り入れている大手企業のケースを紹介します。自社への取り入れ方や個人の働き方をより具体的にイメージするために、ぜひ参考にしてください。オランダにおけるワークシェアリングの事例
オランダにおけるワークシェアリングの導入・実践は、大きな成功例として世界的に認識されています。エネルギーブームの終わりとともに失業率が高まった1980年頃、オランダモデルと呼ばれる労働市場改革がスタートします。1982年に締結されたワッセナー合意の元で、ワークシェアリングが大幅に進み、パートタイム労働者の急増とともに失業率が低下しました。正規雇用者の仕事をパートタイム労働者で分担する方式は、以後さまざまな業界や職種に浸透していきます。現在、教員や公務員などもパートタイム労働者の占める割合は大きい状態です。また、女性や高齢者の働き方にも良い影響を与えました。1987年前後から女性の雇用率がアップ、90年に入るとパートタイム労働者内の高齢者の割合が増加しています。日本国内のワークシェアリング企業事例
日本国内では、自動車業界にてワークシェアリングが導入されてきました。2007年頃のリーマンショックの影響を受け、マツダ自動車は2009年にワークシェアリングを開始します。業績回復を目指し、昼夜2交代制の正規社員約1万人に対して夜間勤務を廃止して、勤務時間を50%削減。1人時間の労働負担を減らすことで、人材を確保しつつ生産性向上を図る取り組みとして、注目を集めました。また、トヨタでは国内21工場において2009年の2〜3月の計11日を操業停止とし、勤務する従業員約3.5万人の休業日を2日ずつ増加して人件費をカットしました。業績向上に向けた固定費の節約目的でワークシェアリングが実施された例です。ワークシェアリングの主な課題3つ
 ワークシェアリングは、適切な形で企業や組織に導入し、効果的に運用することが重要です。導入事例があるとはいえ、効果的に実践するためには、考えなければならない課題も残されています。日本におけるワークシェアリングの浸透に向けて、解決策が必要な主な3つの課題について解説します。今後ワークシェアリングの導入を検討している企業や担当者は、ぜひ参考にしてください。
ワークシェアリングは、適切な形で企業や組織に導入し、効果的に運用することが重要です。導入事例があるとはいえ、効果的に実践するためには、考えなければならない課題も残されています。日本におけるワークシェアリングの浸透に向けて、解決策が必要な主な3つの課題について解説します。今後ワークシェアリングの導入を検討している企業や担当者は、ぜひ参考にしてください。業務フローの見直しに伴う一時的な生産性の低下
ワークシェアリングにより、1人の仕事を複数の人で分担するため、業務フローの修正が必要です。チームや組織でのスムーズな連携が実現するまでは時間と労働力を費やすこととなり、一時的に生産性が低下する可能性があります。担当するチームや組織でのコミュニケーションや業務の品質維持のために、必要な計画を綿密に立てた上で導入を開始すると良いでしょう。また、日本の企業においては、1個人が担当する業務範囲があいまいなケースも少なくありません。準備段階で手間取らないよう、日常的に従業員ごとの業務範囲や業務フローを明確にしておくことも大切です。ワークシェアリング導入に伴う雇用条件の最適化
ワークシェアリングにおける重要な課題に「雇用条件」が挙げられます。ワークシェアリングの概念によりアルバイトやパートといった雇用形態が増える分、従来の正規雇用者の仕事や労働時間が減ります。また、給与などの雇用条件が変わる可能性も出てきます。日本は、フルタイム雇用とパートタイム雇用における賃金の差が大きい状況です。ワークシェアリングによって正規雇用者が非正規雇用に変わり、福利厚生など待遇への影響も考えられます。非正規雇用でも正規雇用同等の待遇を基準とするなど、双方にとって最適なルールを確立する必要があるでしょう。ワークシェアリングにおける副業規定の明確化
働き方の多様化に伴い、副業の扱いも明確にする必要があります。ワークシェアリングによって1人あたりの業務量や労働時間が軽減される分、空いたリソースを使って副業をしたいと考える人も出てきます。また、ワークシェアリングによって給与が減った場合は、副業を余儀なくされる場合もあります。いまだ副業を禁止している企業や組織は少なくない中で、副業を認めるよう方向転換することがワークシェアリングの浸透に必須といえるでしょう。ワークシェアリングアプリおすすめ2選
 ここで、ワークシェアリングを利用できるアプリを紹介します。求職中の方は、自分に合った働き方を実現するために、ワークシェアリングアプリで仕事を探してみましょう。
ここで、ワークシェアリングを利用できるアプリを紹介します。求職中の方は、自分に合った働き方を実現するために、ワークシェアリングアプリで仕事を探してみましょう。Taimee(タイミー)
「Taimee(タイミー)」は、即戦力となる人材と、スポット的に働き手を探している企業をマッチングするアプリです。ワークシェアリングアプリのさきがけ的存在で、2018年8月のローンチ以来注目を集めています。双方の登録条件による自動マッチングにより、従来のアルバイト採用に必要だった応募や面接といったステップを省略しています。また、相互レビューの入力は、職場の状況把握やドタキャンのリスク回避に役立ちます。求職側にとっては、スキマ時間の有効活用が可能となり、雇用側からすると短時間のみの人材補完が可能です。Ucare(ユーケア)
「Ucare(ユーケア)」は、株式会社USEN WORKINGが開発した介護業界に特化したワークシェアリングアプリです。2020年12月に先行登録を開始、その後登録ユーザー数は4,000人を越えるなど、人材不足に陥りやすい介護業界における新しい取り組みとして話題を集めています。勤務が可能な介護施設に欠員が出ると、空いたシフトに適した登録者を自動マッチングして補填します。働き手は自分の経験や保有資格を活かした仕事をしやすく、企業側はスポット的に必要な人員を確保できます。介護補助やドライバー、レクリエーションなど幅広い業務内容で求人を検索可能。また、常勤として長期採用も視野に入れた採用活動ができます。首都圏1都3県から利用がスタートし、将来的には全国展開される予定です。最後に:ワークシェアリングを効果的に導入・実践しよう
ワークシェアリングは、ライフワークバランスの実現や労働状況の最適化に役立つ仕組みで、日本でも徐々に浸透しつつあります。効果的に導入するためには、組織全体における生産性の維持や雇用形態、副業の規定などを事前に明確化することが大切です。自分らしい働き方の実現のために、レンタルオフィスやシェアオフィスなども有効活用しましょう。レンタルオフィス「Re:Zone」は、関西の主要駅近くに複数の拠点を設けています。個人で利用しやすい個室オフィスも多数開設していますので、ぜひご活用ください。