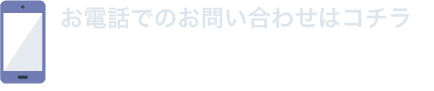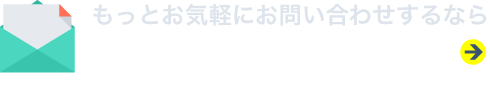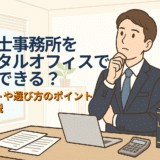建築事務所を開業するためには建築士事務所の登録が必要です。登録には管理建築士の資格が必須であり、建築士としての実務経験も求められます。中には、独立するにあたって開業資金の調達や営業方法などさまざまな不安を抱えている人も多いでしょう。
本記事では、建築事務所の開業に必要な資格や手続き、目安の初期費用についてわかりやすく解説します。建築士としての独立開業に関してよくある質問と回答も紹介しますので、不安を解消し、最初の一歩を踏み出すためにぜひお役立てください。
建築事務所を開業するには何が必要?おおまかな流れ
建築事務所の開業は、おおまかに以下のステップを踏む必要があります。
- 建築士の資格を取得する
- 経験・実績を積む
- 建築士事務所の登録をする
- 管理建築士の講習を受講する
- 建築士として独立・開業する
独立開業に向けて、必要な資格や実務経験、費用の目安などについて次から詳しく解説します。
建築事務所の開業に必要な資格・実務経験
建築事務所を開業するには、建築士の資格を取得した後、設計事務所や工務店などで実務経験を積んで、建築士事務所としての登録を行う必要があります。
また、建築士事務所の登録には、管理建築士の設置が必須であり、自ら資格を取得するか、有資格者に所属してもらうことになります。
建築士事務所の登録とは
建築士法第23条において、以下のような業務を行う場合、事前に建築士事務所として登録することが義務づけられています。
- 建築物の設計に関する業務
- 建築物の工事監理に関する業務
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督に関する業務
- 建築物に関する調査または鑑定に関する業務
- 建築物の建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理に関する業務
建築事務所を開業するためには、基本的に登録が必要です。受注する業務が上記に当てはまるか判断が難しい場合は、無登録のまま営業を始めず、建築士事務所協会もしくは行政書士に相談しましょう。
建築士事務所の登録手続き
建築士事務所の登録を行うためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 事務所が確保されていること
- 管理建築士が常勤で1名以上在籍していること
- 一定の欠格要件に該当しないこと
- 会社の場合は登記目的に「建築物の設計・工事監理」などが含まれること
- 納税証明が取れること(新設法人の場合は法人開設届の提出)
登録手続きは、主に以下の手順で進めます。
- 書類の収集と作成
- 建築士事務所協会へ書類提出
- 手数料の納付
- 審査
- 登録証の交付
建築士事務所の登録申請書を提出してから、登録が完了するまでの期間は1週間が目安です。提出する書類の種類は多いため計画的に準備しましょう。
管理建築士とは
建築士事務所の登録に必要な管理建築士とは、名前の通り「建築士事務所を管理する建築士」を指します。建築士の種類によって、「一級建築士事務所」「二級建築士事務所」「木造建築士事務所」に分かれます。
管理建築士になるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 建築士(1級・2級・木造いずれか)の資格を有していること
- 3年以上の設計・工事監理の実務経験があること
- 所定の管理建築士講習を修了していること
建築士の資格を取得した時点では、建築事務所を開業することはできず、実務経験と講習が必要です。また、一般的に管理建築士は専任性が必要で、常勤して職務を行います。そのため、他の企業に在籍している従業員や派遣社員は、管理建築士としては認められません。
加えて、他社の代表取締役や他の法令によって専任が義務付けられている人は、原則として管理建築士になることができない点にも注意が必要です。ただし、建設業許可上の専任技術者や宅建業免許上の専任取引主任者など、管理建築士との兼務が認められるケースもあります。
建築事務所の開業にかかる費用目安と資金調達方法
建築事務所の開業を検討する上で、どのくらいの費用がかかるのか気になる人は多いでしょう。ここでは、開業費用の目安や、補助金や助成金を含む資金調達方法について紹介します。
初期費用の目安
建築士の独立開業における初期費用は、約500万円が目安とされています。費用の内訳は、事務所の契約や登記申請、デスク・椅子などの家具、パソコンやプリンターといった備品費などです。
また、従業員を雇う場合、毎月の給与や社会保険料などもかかります。すぐに仕事を受注できない可能性もあるため、仕事が軌道に乗るまでの生活費を確保しておくことも大切です。
利用できる資金調達方法
建築事務所を開業する際の初期費用を、以下のような方法で資金調達するという選択肢もあります。
- 日本政策金融公庫(創業融資)
- 地方自治体の制度融資
- 民間銀行のビジネスローン
- 補助金・助成金
- 家族や知人からの借り入れ
日本政策金融公庫の創業融資は、無担保・無保証でも借りやすく、開業時の融資として人気があります。銀行など金融機関の融資は、審査は厳しめですが実績があると有利でしょう。
建築士が独立開業に利用できる助成金・補助金
建築士の独立開業時に利用できる補助金や助成金には、以下のようなものがあります。
- 雇用調整助成金
- キャリアアップ助成金
- 両立支援等助成金
- 小規模事業者持続化補助金
- IT導入補助金
- ものづくり補助金
上記はいずれも原則として申請が通ってから支給される後払い方式のため、開業資金には利用できない点に注意が必要です。受給条件などの詳細はホームページで確認した上で申請しましょう。
建築士の開業でよくある失敗と成功のコツ
建築事務所の開業でよくある失敗とその対策について解説します。失敗を回避し、成功するためのポイントを押さえておきましょう。
資金管理がうまくいかない
すぐに受注が決まるとは限らず、収入が不安定になる可能性もあります。安定的な資金管理のために、開業資金とは別に生活費を含む運転資金を最低限確保しておくことが重要です。
案件を獲得する際には、下請けよりも元請けの仕事を狙うことで、単価や収入が安定しやすく、継続的な依頼につながります。独立前にはクレジットカードの準備も行っておくと安心です。
営業・集客がうまくいかない
独立後は自分で仕事を獲得しなければならず、営業や集客の力が問われます。具体的な営業方法には、以下があります。
- SNSやホームページで情報発信を行う
- 知人や過去の顧客から紹介を受ける
- 独立・フリーランス向けマッチングサービスを活用する
- 建築コンペでの受賞を目指す
- 地域密着型のチラシや広告を利用する
SNSアカウントを開設し、ホームページへ誘導することで見込み客からの問い合わせが期待できます。また、案件紹介エージェントの活用や建築コンペへの参加も有用です。積極的に人脈を広げながら、継続的に営業活動を行うことが大切です。
年収が上がらない
建築士として独立開業すると、年収アップが見込めますが、収入を安定して増やすために工夫が必要です。建築士と関連する資格を取得すると、仕事の幅が広がり、収入が上がる可能性があります。代表的な資格には、次のようなものがあります。
- 宅地建物取引士
- 1級建築施工管理技士
- インテリアコーディネーター
資格取得を通じてスキルの幅を広げられれば、他社との差別化にもつながります。
まとめ
建築事務所を開業するにあたって、管理建築士の資格や建築士事務所の登録などの要件があります。一般的な初期費用は約500万円とされ、創業融資や補助金・助成金を利用することも可能です。
建築士は独立後もニーズのある職業ですが、安定した経営には事前準備が欠かせません。資金計画や集客に向けた人脈づくりなどを丁寧に行うことで、トラブルを防ぎ、開業の成功につなげることができます。
レンタルオフィス「Re:ZONE」では、創業期のスタートアップや小規模事業者に最適な個室タイプのプライベートオフィスを提供しています。独立開業時の事務所として利用可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。