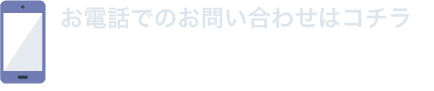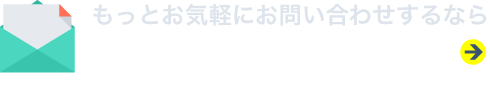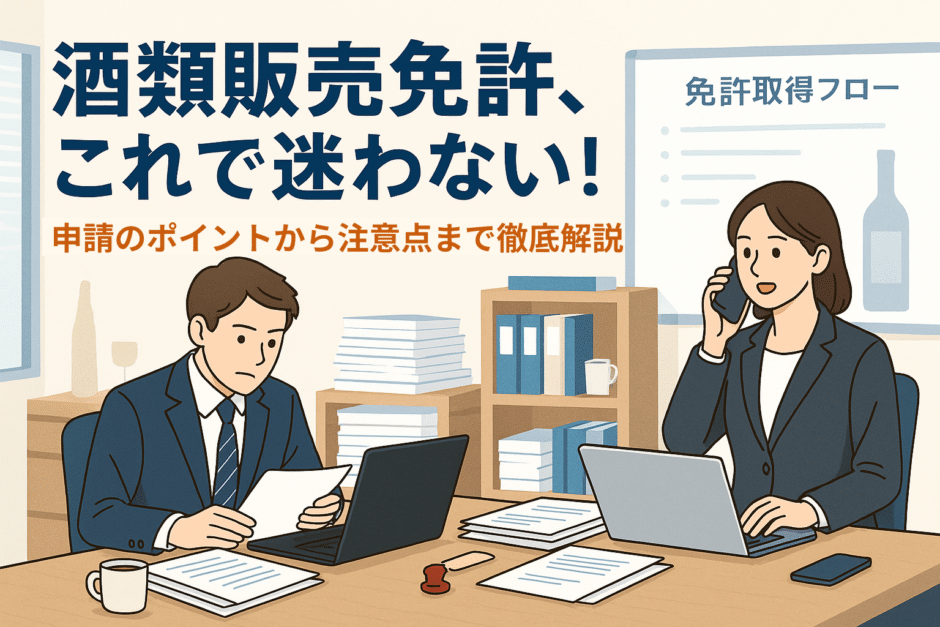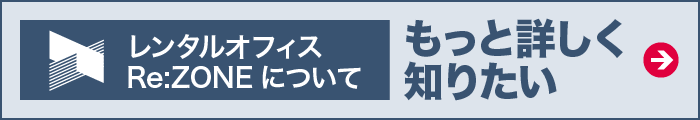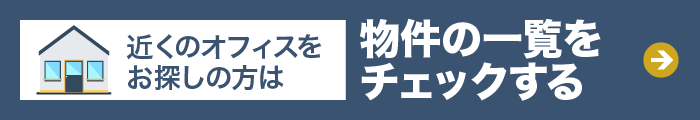飲食店でお酒を提供する場合や、ECサイトでのお酒を販売したい場合に必要なのが酒類販売免許です。酒類販売免許が必要な事業を営む際に、(免許を)取得せずにお酒を販売すると法律違反となり、罰則の対象になるため注意が必要です。
酒類販売免許には複数の種類があり、初めての人にとって申請方法や必要な書類などががわかりにくい場合もあるでしょう。
本記事では、酒類販売免許が必要な事業や免許の種類、取得方法、申請費用などについて詳しく解説します。これから酒類販売ビジネスを始めようと検討している人は、ぜひ参考にしてください。
酒類販売免許とは
酒類販売免許とは、お酒を販売するために必要な国税庁の許可です。営利目的か否かによらず、酒類を継続的に販売するためには酒類販売免許が必要です。酒税法の規定に基づいて、事業の形態に合った免許を取得し、適切な運営を行うことが求められます。
免許を取得することで、法律に沿った形で酒類を取り扱うことができ、ビジネスの信頼性も高まります。
酒類販売免許が必要な事業形態
酒類販売免許は、酒類を仕入れて販売するすべての事業者に必要です。例えば、酒屋やスーパー、飲食店のテイクアウトなどが該当します。また、ECサイトや通信販売でお酒を扱う場合、業務用の卸売業者も特定の免許が必要です。
酒類販売免許なしで販売できるケース
例えば、飲食店での店内提供には免許が不要ですが、店外販売やテイクアウトには免許が必要です。
また、海外で酒類を購入して個人消費目的で国内に持ち込むケースも、免許なしで問題ありません。ただし、イベントや露店などで販売する場合は、期間限定の免許が必要になるケースもあるため事前に確認が必要です。
酒類販売免許の種類と違い
酒類販売業免許には種類があり、販売先や販売方法によって以下3種類分けられます。
- 酒類小売業免許:一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許など
- 酒類卸売業免許:全酒類卸売業免許、洋酒卸売業免許、自己商標卸売業免許など
- 酒類販売媒介業免許
各免許について、詳しく解説します。
酒類小売業免許
酒類小売業免許とは、一般消費者や飲食店を対象として酒類の販売を行うための免許です。酒類小売業免許は、さらに以下2つに区分されます。
- 一般酒類小売業免許:コンビニや酒屋など店舗で酒類を販売するための免許
- 通信販売酒類小売業免許:EC販売やカタログ通販などによって酒類を販売するための免許
ただし、インターネット上で外国の購入者向けに酒類を販売する場合、「一般酒類小売業免許」が必要です。また、注文はインターネットで受け付けて、近隣に配達して商品を届けるケースも「一般酒類小売業免許」の対象です。
さらに、通信販売酒類小売業免許で販売できる国産酒類には制限もあります。事前に条件をよく確認した上で申請することが重要です。
酒類卸売業免許
酒類卸売業免許は、酒類販売業者や製造者などを対象とする卸売販売に必要な免許です。細かな種類に分けられており、代表的なものを以下に示します。
- 全酒類卸売業免許:輸入・輸出を含め原則としてすべての品目の酒類を卸売するための免許
- 洋酒卸売業免許:ワインやリキュールなど免許された洋酒を卸売するための免許
- 自己商標卸売業免許:自ら開発した商標もしくは銘柄の酒類を卸売するための免許
いずれの免許でも、扱う酒類の品目や仕入れ値、販売価格、年間の収支見込、取扱数量、販売対象の地域などを細かく記載した事業計画書を提出する必要があります。
酒類販売媒介業免許
酒類販売媒介業免許は、酒類を直接販売するのではなく、他人間の酒類の売買取引を成立させる媒介業務に必要な免許です。例えば、酒類専門のオンラインサイトやオークションサイトなど、売り手と買い手をマッチングする業務を行う際に取得する必要があります。
自社で在庫を持たず取引のサポートを行う立場であるため、前述の酒類販売業免許とは異なる基準で審査されます。
酒類販売免許の取得方法と必要書類
酒類販売免許を取得するためには、一定の要件を満たしている必要があります。また、申請には多くの書類が必要なため、計画的に準備することが重要です。ここでは、酒類販売免許の申請条件と審査基準、必要な書類について詳しく解説します。
取得条件と審査基準
酒類販売免許で満たすべき主な条件として、以下の項目があります。
- 場所の要件:酒類の販売・提供を予定している場所が適切か
- 経営基礎要件:免許を取得し酒類販売を予定している者(法人/個人)の資金や経営状態が、酒類販売にふさわしいか
- 人的な要件:税金の滞納処分の経歴、各種法令違反や罰則の有無(一定期間が経っているか)
- 需要調整要件:酒類の仕入れ・販売を適正なやり方で行えるか、販売価格や品質などを適正に保てるか など
審査の際には細かくチェックされるため、計画的に準備することが重要です。
申請に必要な書類一覧
酒類販売免許の申請に提出する主な書類は、以下の通りです。
- 申請者の履歴書
- 店舗の図面や販売場所の契約書等の写し
- 土地・建物登記事項証明書
- 地方税納税証明書
- 酒類販売業免許申請書チェック表
- 酒類販売業免許の免許要件契約書
- 個人の場合:住民票、最近3年間の収支計画書 など
- 法人の場合:履歴事項全部証明書、定款、3事業年度の財務諸表 など
書類に不備があると審査が遅れるため、事前にチェックリストを用意して準備を進めると良いでしょう。
酒類販売免許の取得費用・申請プロセス
酒類販売免許の取得には、申請費用がかかります。また、申請プロセスは最短で2ヶ月前後と言われていますが、書類不備や追加の確認などがあればさらに時間を要します。
取得費用
酒類販売免許の申請には、1申請あたり3万円の登録免許税がかかります。また、卸売業免許の場合には、1申請につき9万円を支払います。行政書士などの専門家に依頼する場合、合計で数万円から数十万円の費用がかかります。
事業に必要な設備などの初期投資も考慮し、十分な資金を確保するために、綿密な事業計画の作成が重要です。
申請から取得までの流れと期間の目安
酒類販売免許の申請は、おおむね以下の流れで進めます。
- 取り扱うお酒の品目や種類、販売方法、対象者などを明確にし、どの免許が必要か確認する
- 申請に必要な書類を収集する
- 申請書類を作成する
- 税務署に書類を揃えて提出する
- 審査が終わり、免許通知書の交付日の日程調整依頼が届く
審査には通常2〜3ヶ月ほどを要します。申請書類に不備がある場合や、現地調査などの追加確認が必要な場合などはさらに時間がかかります。免許申請に関して不安がある場合は、事前に税務署などに相談しておくと安心です。
酒類販売免許についてよくある質問
酒類販売免許に関するよくある質問と、その回答を見ていきましょう。
申請が却下されることはある?対策は?
書類の不備や申請者の経歴に問題があるなどで、申請が却下されることがあります。また、販売場所の設備要件など要件を満たしていない場合も、審査に通りにくいため、事前に要件を確認するとともに、専門家の意見も仰ぐと良いでしょう。
免許取得後の管理義務とは?違反するとどうなる?
酒類販売免許を取得した後は、管理義務を守る必要があります。主な義務は、酒類の販売記録の保存(記帳義務)や、毎年の税務署への報告(申告義務)、未成年者への販売防止対策などです。販売記録は税務署からの監査時に求められる場合があるため、適切に保管しましょう。
免許更新は必要?タイミングと手続きは?
酒類販売免許には有効期限がないため、基本的に更新手続きは不要です。ただ、事業内容の変更や営業所の移転などがある場合は、税務署への届出が必要になります。また、法人として免許を取得していて、代表者の変更があれば届出が求められる場合もあります。
酒類販売免許取得のポイントを押さえて事業を成功させよう
酒類販売免許は、お酒を販売するために必須となる国税庁の許可です。複数の種別があり、事業の形態に応じて適切な免許を取得する必要があります。違反すると免許の取り消しや罰則の対象になるため、法令遵守が重要です。
最新の情報を国税庁のサイトなどで確認しつつ、計画的に準備を進めましょう。また、酒類販売事業者としてスムーズに運営するためには、環境を整えることも重要です。
レンタルオフィス「Re:ZONE」は、スモールビジネスや個人起業家の活動に最適なプライベートオフィスを提供しています。万全なセキュリティで、設備も充実しています。この機会に詳細をご覧いただき、お気軽にご相談ください。